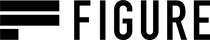markaが考える
ものづくりの原点
2003年に設立されたmarkaの魅力は、大人のためのハイエンドなガーメント。これまで、デザイナーの石川俊介さんが培ったヴィンテージへの審美眼やアメリカ、ヨーロッパへの憧憬をメイド・イン・ジャパンで繊細かつ丁寧に表現して人気を博してきました。しかし近年は、より「生地」にフォーカスが注がれています。インタビューの前半は、氏のこだわりの中でもとくに強い、3つの生地について。後半は、ものづくりの表現についてお話を伺いました。
Photo:Kanta Matsubayashi / Production:MANUSKRIPT
石川俊介さん(以下石川):いろんな制約が年々増え、面白いことがどんどんできなくなり、昔のように自由な雰囲気がなくなりつつあります。自由かどうかはさておき、やりがいについて考えるようになりました。僕たちはもともといわゆる小さな「ファッションの村」にいたんです。それをファッション誌に紹介いただいて大きくなり、有名になっていった。しかしこれがだんだん高齢化、過疎化して、その横にできた大きな「インターネットシティ」が急速に盛り上がっているのが現状。この村をはやく飛び越えなくては、と強く感じています。

石川:どれだけ質が高くても、ユーザーの人たちが求めるものと作っている服が合致しなくてはただの自己満足でしかなく、社会的価値を失うかもしれません。SNSが主流になっているこの世の中が求めているクオリティとは?とデザインとビジネスの両方をやっている人間として考えるようにもなりました。音楽業界で言えば、サブスクリ プションで音楽を聴くのではなく、わざわざレコード店に足を運んで掘って買うようなマーケットが、ファッション業界にどれだけあるか、自分がやりたいことを全部詰め込んだ服を買ってくれる顧客がどれだけいるのか。ついついネガティブに考えてしまいがちですよね。でもやっぱり僕はものづくりが好きなので、価格が高くてもクオリティの高さを全力で追求したいんです。

石川:まずはブラックアルパカです。ペルーの標高4000mを超えるエリアにある牧場に、僕は何度も訪れました。そこで飼育されている黒のアルパカだけを集めて作った生地です。その生産量はアルパカ全体の1%にも満たないと言われています。1960年代以降、アルパカを使ったとある有名なゴルフ用のニットが流行したことで、どんな原色に染められる白ばかりが産地で育てられました。他の色がどんどん少なくなる中、1980年代に僕の親戚が、有色のアルパカを増やそうと大きな繊維会社と取り組んできたんです。今になってようやくブラックアルパカの頭数が増えてきたので、日本で生地にしました。希少性はもちろんのこと、スムーズな肌さわりや光沢が素晴らしい。世界中探しても、MARKAWAREでしか扱っていないと思います。

石川:これは見ての通り、自立する生地なんですね。もともと防水・撥水効果の高いコットン100%の有名なベンタイルという高密度の英国生地があるのですが、それを超える高い密度を、オーガニックコットンで織ったものです。まるで頒布のようにガッチガチに極限まで打ち込んで強度を高めています。仕上げの状態では水を入れていますが、洗いもかけていません。もうバリバリで、オリーブやブラックなんてまるで昆布みたいですよ(笑)

石川:これだけ密度が高いと色も染まらないので、糸の状態で染める「先染め」をしています。ワークウェアやミリタリーウェアなどに使われる、色落ちがしにくくて堅牢度の高いスレン染料を使っていて、昔のバーバリーの生地などにも用いられていました。あれって何十年たっても色褪せないですよね? 耐久性が高いから、長く着ていただける。しかもコットン100%なので耐水圧がありながら、アウトドア系のスリーレイヤーとは違って蒸れにくいところが気に入っています。

石川:あと一つはサバイバルクロスがいいかな。これ、何かというとギャバですね。普通のギャバジンは双糸といって2本の糸を撚ったものですが、これは三子撚りといって、3本の糸を使っています。これにより強度が高まり、耐久性が上がっているので僕は「サバイバルクロス」と名づけました。この色に関すると、縦糸と緯糸の色が異なるシャンブレー組織です。じつはブルーとオレンジを掛け合わせることで、玉虫色のようなオリーブっぽい色を表現しているんです。

石川:これをウール100%っていうところが面白いのですが、さらにオーガニックなんです。アルゼンチンのパタゴニア地方で見つけました。オーストラリアのオーガニックウールを使っていたことも過去にありますが、持続性がなくてほとんどなくなってしまった。そこで南米の牧場に直接行って、直談判して使わせてもらっているんです。ちなみにそこの牧場に来た日本人は、僕が二人目だそうです。
石川:日本の繊維会社とか、商社が入っているケースもあるんですが、基本的に独自で探してコンタクトをとって「御社の生地を使いたい」って交渉しますよ。やっぱり直接会って話したほうが熱意も伝わるし、喜んでもらえる。仲介業者が入ると、ロット数とか金額などの条件が厳しくなることも多いですから。
石川:それこそ90年代は、そういう宝探しを誰もが楽しんでいたじゃないですか。僕も若い頃は、既に掘り尽くされたと言われていたジーンズや、次の金脈だったスニーカーを国内、アメリカと片っ端に探していましたよ。イエローページ(海外の電話帳)をしらみつぶしに見て電話したりしてね。ファクトリーや生地探しは、それと同じことを、違うスケールでやっている感覚です。あの興奮やワクワクを一度覚えたら、もう一生忘れられない。そんな感じで、単身で乗り込んでいます。

石川:やはりリファレンスをどれだけ多く持っているかだと思います。僕らがラッキーだったのは、ちょうど物が日本に集まってきた世代だったこと。世の中の良質なヴィンテージを日本人が買い漁っていたし、世界中の新しいブランドの起こりを日本で深く見れたことは財産であり、その掛け算がデザインにつながっていると思います。服の進化は90年代からある程度止まっているので。スニーカーは進化していますけど。
石川:そうですね。最近のインプットは過去の焼き直しをリミックスすることで新しさを表現しているので、その基礎をどれだけたくさん自分がもっているかが大事だと思います。

石川:確かに最初のコンセプトはメイド・イン・ジャパンで、日の丸のタグをつけていました。この頃は世の中がアジアに生産拠点を移していた頃で、日本のものづくりの衰退が危ぶまれたタイミングでした。だから国内の産地、そこにいる職人の仕事に注目して、いいものを作りたい気持ちをずっと持ち続けていました。しかし2014年頃からトレーサビリティ(*原料の調達から生産、消費までのサプライチェーン全体の各工程を追跡可能な状態に落とし込むこと)をMARKAWAREのタグに入れるようになってから、原料への疑問がいろいろと生まれ、その後数年かけてサステナビリティ(*環境に配慮した素材の衣服を作ること)へと進化していきました。生産環境なども含めてよりよい原料を求めて、国内から海外にまた飛び出していった感覚です。

石川:職人も高齢化が進み、昔ほどのエネルギーは感じにくくなったのは確かです。しかしいざ海外に再び出てみたら、すごい熱量をもってものづくりしている人たちがいることに気づきました。東南アジアでも若い世代が工場を立ち上げて、本気でジーンズ作ってたりするんです。日本ではルーティーンワークになってしまった工程を、すごく研究して頑張っている。それをサポートするのが、日本人の役割じゃないかな、って思い始めたんです。
石川:たしかにそうかもしれません。しかし彼らを見てると興奮しちゃって、新しいものを一緒に作りたい気持ちも強くなってきたんですよ。アジアのダイナミズムみたいなものを、もっと伝えていきたいなって。

石川:服以外の部分でいうなら、やっぱり「旅」と「食」で間違いありません。オーガニックな素材を使うことやサステナブルへの興味関心はすべて食から来ています。僕が展示会で説明をいっぱいする理由は、いいレストランはきちんと伝えてくれるから。どこで採れたか、それをどう調理しているかを先に理解して食べると、美味しさも全然違うんですよ。それは服も同じことだと思います。料理人がオーガニックな農作物を料理していることと同じように、僕が天然素材を色々な工場で加工することと、同じですから。
石川:そして旅は、僕の人生のテーマでもあります。若い時から好きな作家といえば、ブルース・チャトウィンでしたし、小学校の頃、雑誌の表紙で見て、すごい冒険家だなって思っていた植村直己は、永遠のヒーローです。もっと前なら、物心ついた頃にテレビで見ていた「兼高かおる世界の旅」が好きだったことも影響しているかもしれません。いろいろな書籍で読んできた海外の探検ものと服を作るのが好きな自分が掛け算されて、いまのスタイルができあがったと思います。

石川:どうしても自己表現が先にあり、後から服がついてくる時代であることは理解しているので、SNSを利用していろいろ発信していますが、できれば今後は僕自身が露出せず、裏方に回っていきたいなと思います。今はそのための仕組み作りの時期ですね。こっそり、じっくり没頭する僕のものづくりに賛同してくれた表現者たちが、服の魅力を広めてくれたら理想ですね。それは昔から変わらないメディアの姿だと思います。

marka / MARKAWARE デザイナー
石川俊介 1969年、兵庫県生まれ。学生時代からファッションが好きで、古着やスニーカーの買付けなどを積極的行う。大学卒業後は経営コンサルティングの会社に勤務。2002年にレディースブランド、マーカ(marka)をスタート。レディースブランドとしてスタートしたが、2003年からメンズラインを始動。09年に「マーカウェア(markaware)」をスタートする。11年に東京・中目黒に直営店「PARKING」をオープン。19年秋冬より、サステナビリティを打ち出したブランド「テクスト(text)」を展開。